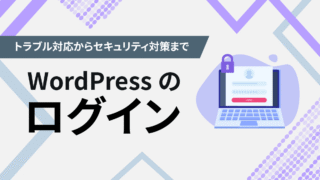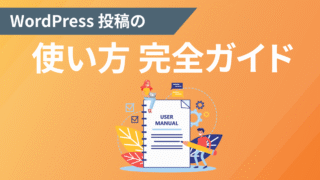サイトを運営する上で、「情報の整理が難しい」「訪問者が目的の情報をスムーズに見つけられない」といった課題に直面していませんか?
特にWordPressの初心者の方にとって、記事の分類方法は悩ましい点かもしれません。
この記事では、そうした課題を解決するWordPressの重要な機能「カテゴリー」について、初心者の方にも理解しやすいように解説します。小規模法人のウェブ担当者の方も、自力で集客サイトを立ち上げたい個人事業主の方も、この機能を適切に活用することで、サイトの構造が整理され、訪問者と検索エンジルの双方にとって利便性の高いサイトへと改善できます。
低コストで効率的に、そして効果的なサイトを構築するために、WordPressのカテゴリー機能をぜひご活用ください。
そもそもカテゴリーって何?記事を分類する「棚」をイメージしよう
カテゴリーとは、WordPressにおける記事の分類項目です。
これを理解するためには、書籍をジャンル別に並べる「棚」をイメージすると分かりやすいでしょう。
たとえば、書店では小説、ビジネス書、専門書など、ジャンルごとに書籍が整理されています。この「ジャンル別の棚」が、WordPressにおける「カテゴリー」に該当します。
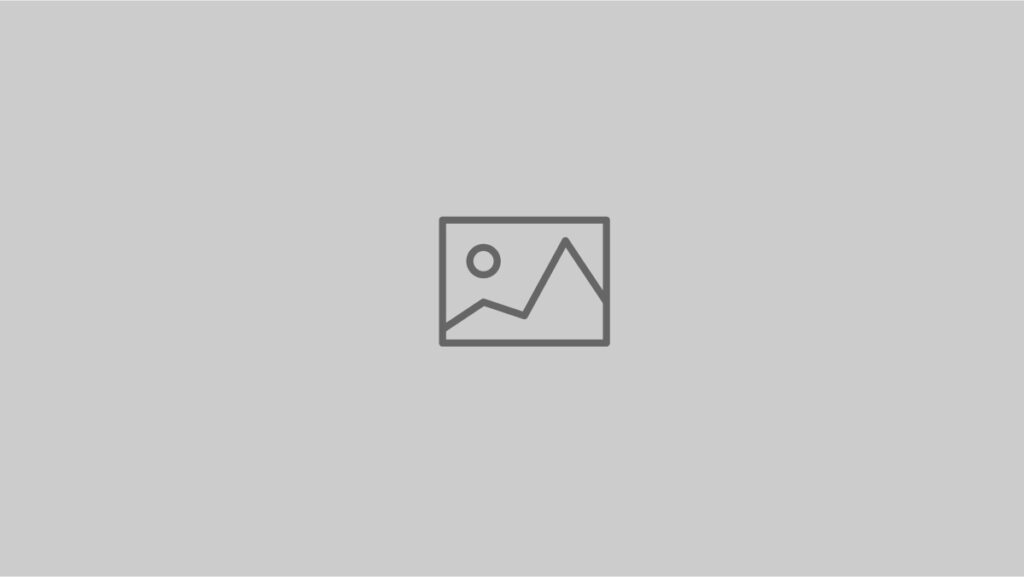
ウェブサイトにカテゴリーを設定しない場合、すべての記事が順不同で表示されることになります。これは、本がすべてごちゃ混ぜに置かれた書店のようになり、訪問者が目的の情報を見つけるのに手間取ってしまいます。
しかし、カテゴリーによって記事を適切に分類することで、訪問者は探している情報がどの「棚」(カテゴリー)にあるのかを容易に把握でき、スムーズに目的の情報にたどり着くことができます。
たとえば、リフォーム会社のサイトであれば「施工事例」「お客様の声」「よくある質問」といったカテゴリー、士業の方であれば「業務内容」「実績紹介」「セミナー情報」などが考えられます。
WordPressでカテゴリーを活用することは、サイト全体の構造を明確にし、訪問者の利便性を向上させるだけでなく、検索エンジン(Googleなど)にサイトのコンテンツ内容を正確に伝える上でも重要です。
まずは、「記事を整理するための分類機能」と捉えてください。
なぜカテゴリーが重要なのか?訪問者にもGoogleにも優しいサイトへ
WordPressにおけるカテゴリー設定は、単なる記事の分類以上の意味を持ちます。
それは、あなたのサイトを訪問者にとって使いやすく、かつ検索エンジンにとっても評価されやすい構造にするための基盤となるからです。
訪問者にとってのメリット:迷子にならない、必要な情報にたどり着きやすい
サイトに訪れる人は、特定の目的や知りたい情報を持ってアクセスします。カテゴリーが適切に設定されていると、訪問者は以下の点で恩恵を受けます。
- 情報への迅速なアクセス:サイトのメニューやサイドバーに表示されたカテゴリーを見るだけで、どのような情報が提供されているのかを直感的に把握できます。「施工事例」を探している人はそのカテゴリーをクリックすれば、関連情報が一覧で表示されます。
- サイト構造の理解促進:サイト全体がどのようなトピックで構成されているのかが明確になり、訪問者は自分のいる場所と、他にどんな情報があるのかを理解しやすくなります。これは、まるで整理整頓された図書館で目的の本を探すような感覚です。
- サイト滞在時間の延長:関連性の高い記事がカテゴリーごとにまとまっているため、訪問者は次々に興味のある記事を読み進めやすくなります。結果としてサイトの滞在時間が延び、エンゲージメントの向上につながります。
もしカテゴリーがなければ、訪問者は目的の情報を見つけるためにサイト内をさまよい、最終的には離脱してしまう可能性が高まります。
これでは、せっかく獲得した見込み客を逃すことになりかねません。
Google(検索エンジン)にとってのメリット:サイト構造が理解され、評価されやすくなる
ウェブサイトの情報を検索エンジンに適切に伝えることも、カテゴリーの重要な役割です。
Googleのような検索エンジンは、サイトの構造や内容を理解して、ユーザーの検索意図に最も合ったページを提示しようとします。
- サイトテーマの明確化:カテゴリーによって各ページのテーマが整理されていると、検索エンジンはサイト全体が何についての情報を提供しているのか、また各ページがどのトピックに属するのかを正確に把握しやすくなります。
- クローラーの効率的な巡回:検索エンジンのクローラー(情報を収集するプログラム)は、サイトのリンク構造をたどってページを巡回します。カテゴリーが明確に設定されていると、クローラーは効率的に関連ページを認識し、サイト内の重要なコンテンツを見逃すことなくインデックス(登録)しやすくなります。
- 検索順位への影響:検索エンジンは、ユーザーにとって価値のある情報を提供し、使いやすいサイトを高く評価する傾向があります。整理されたカテゴリーは、ユーザー体験の向上に貢献するため、間接的に検索順位にも良い影響を与える可能性があります。
特に、小規模法人や個人事業主の方々が、限られたリソースでウェブ集客を行う上では、カテゴリーによるサイト最適化は非常に費用対効果の高い施策と言えます。
WordPressでカテゴリーを設定する基本ステップ
ここからは、実際にWordPressでカテゴリーを設定する方法を解説します。
手順どおりに進めれば簡単に設定できますのでご安心ください。
新規カテゴリーの作成方法:直感的に設定できる!
WordPressで新しいカテゴリーを作るのは非常に簡単です。
- WordPressの管理画面にログインします。
- 左側のメニューから「投稿」にカーソルを合わせ、「カテゴリー」をクリックします。
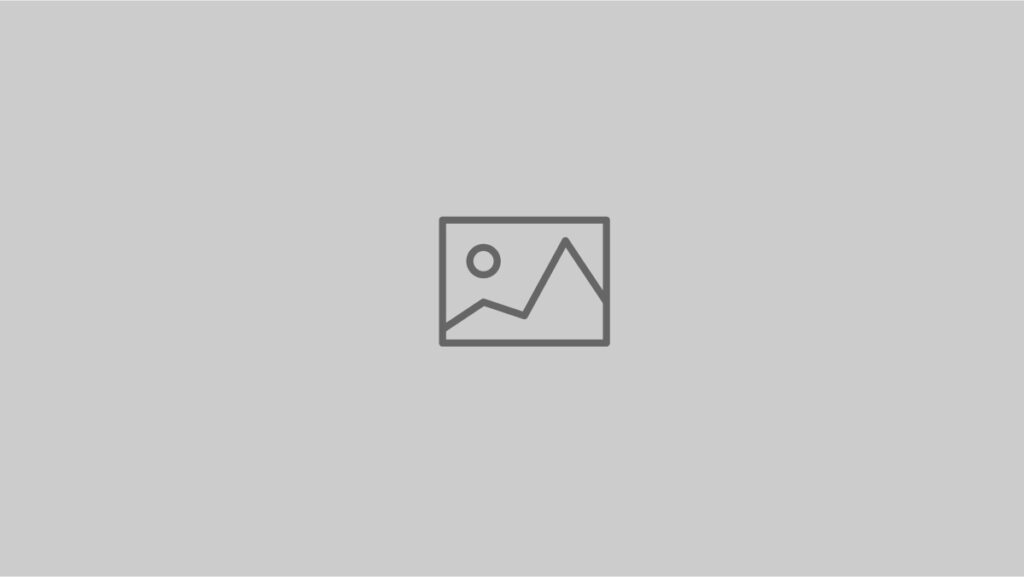
- カテゴリー管理画面の左側に「新規カテゴリーを追加」という項目があります。
- 「名前」の欄に、作成したいカテゴリー名を入力します。たとえば「施工事例」「お客様の声」「イベント情報」など、分かりやすい名前をつけましょう。
- 「スラッグ」の欄は、そのままでも構いませんが、通常はカテゴリー名を半角英数字(ハイフンでつなぐ)で入力します。これはURLの一部になる部分です。たとえば「施工事例」なら「seko-jirei」などと入力します。スラッグについては後ほど詳しく解説します。
- 「親カテゴリー」は、もし作成するカテゴリーが既存のカテゴリーの下にくる場合(たとえば「料理」カテゴリーの下に「和食」や「洋食」などを置く場合)に選択します。最初は「なし」で大丈夫です。
- 「説明」の欄は、カテゴリーの簡単な説明を入力できますが、必須ではありません。一般的にサイト上に表示されることは少ないです。
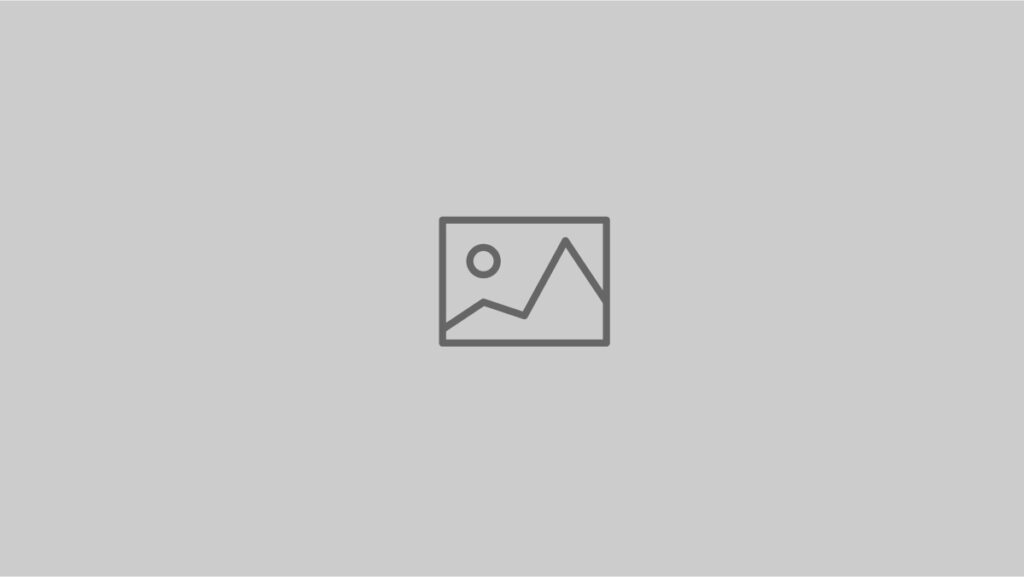
- 最後に「新規カテゴリーを追加」ボタンをクリックすれば、新しいカテゴリーが作成されます。
記事へのカテゴリー割り当て方:簡単チェックで設定完了
カテゴリーを作成したら、次はそのカテゴリーを記事に割り当てていきましょう。
- 記事を作成、または既存の記事を編集する画面を開きます。
- 画面右側にあるブロックエディターのサイドバーに「投稿」タブから「カテゴリー」を選択
- ここに、あなたが作成したカテゴリーが一覧表示されています。記事に割り当てたいカテゴリー名の左側にあるボックスにチェックを入れるだけです。
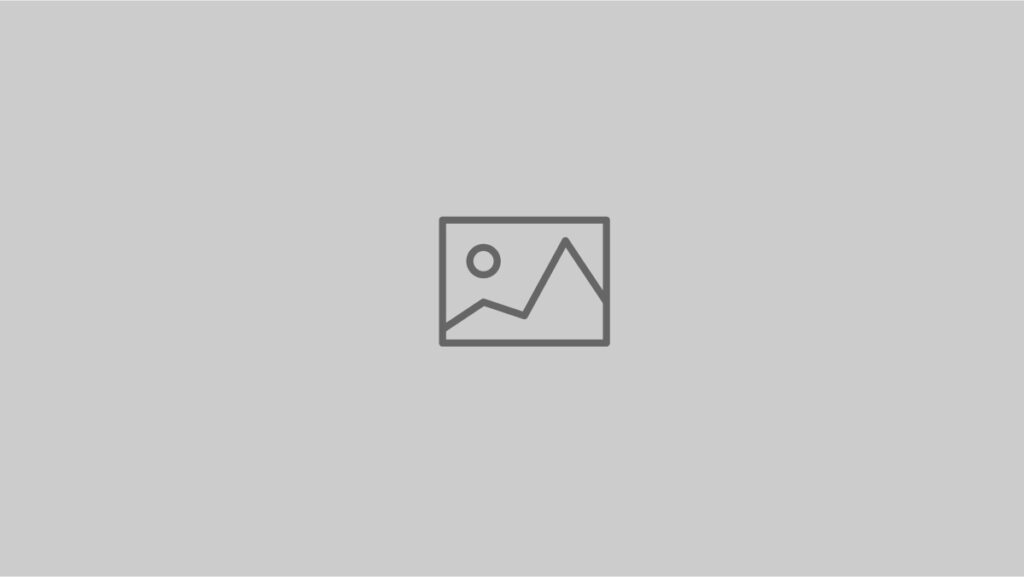
- 最後に、記事を「更新」または「公開」すれば、設定したカテゴリーが記事に適用されます。
カテゴリーの表示設定:メニューやサイドバーに表示させよう
カテゴリーを作成し記事に割り当てただけでは、サイトの訪問者はその存在に気付かないかもしれません。
作成したカテゴリーをサイト上に表示させ、訪問者がアクセスできるようにしましょう。主な表示方法は「ナビゲーションメニュー」と「サイドバー(ウィジェット)」です。
ナビゲーションメニューに表示する場合
サイト上部のグローバルメニューやフッターメニューなど、サイト全体の案内役となるメニューにカテゴリーを追加する方法です。
- WordPress管理画面の左側メニュー「外観」から「メニュー」をクリックします。
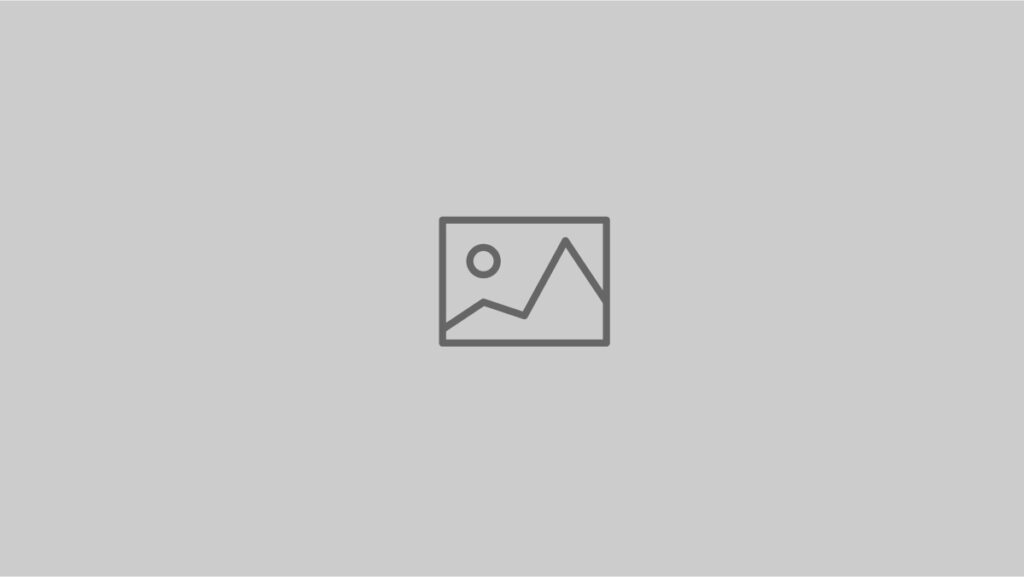
- メニュー編集画面の左側にある「メニュー項目を追加」のブロックから「カテゴリー」を展開します。
- 表示したいカテゴリー名の左にあるチェックボックスにチェックを入れ、「メニューに追加」ボタンをクリックします。
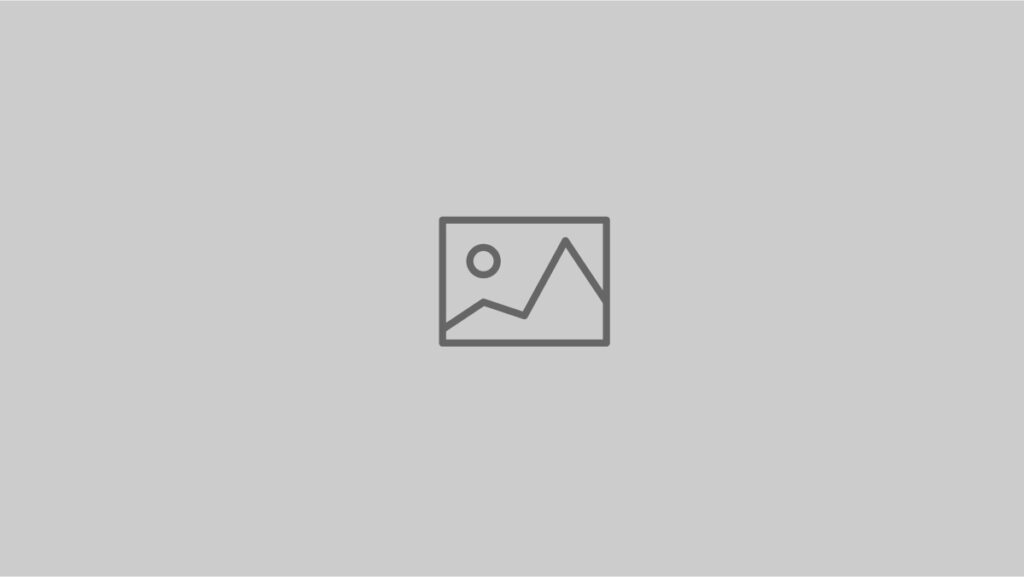
- 追加されたカテゴリー項目をドラッグ&ドロップで好きな位置に配置できます。階層をつけたい場合は、少し右にずらして配置すると親子関係になります。
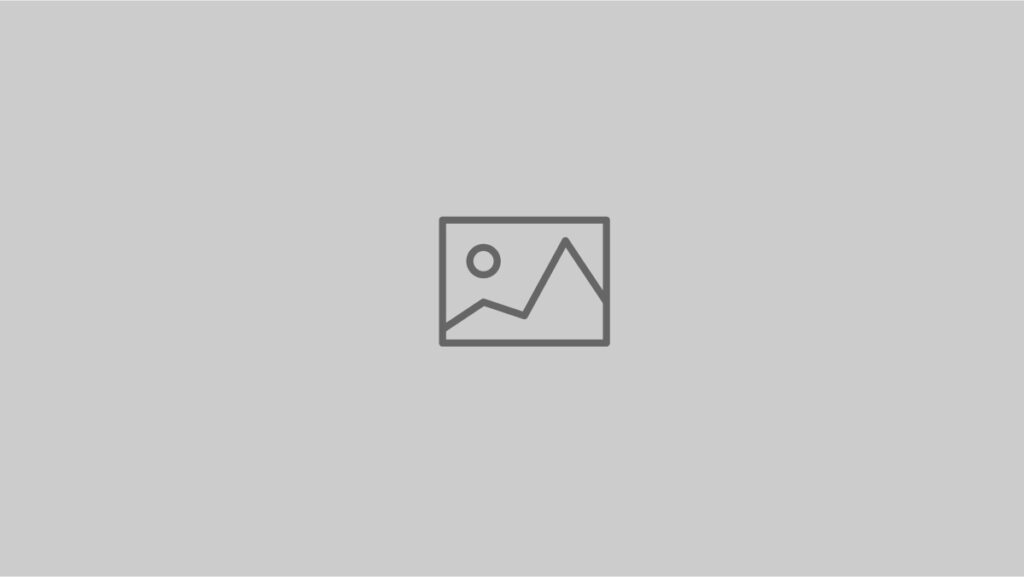
- 最後に右下の「メニューを保存」ボタンをクリックすれば、サイトにカテゴリーが表示されます。
サイドバー(ウィジェット)に表示する
ブログ記事一覧ページや単一記事ページなどのサイドバーに、カテゴリー一覧を表示させる方法です。
- WordPress管理画面の左側メニュー「外観」から「ウィジェット」をクリックします。
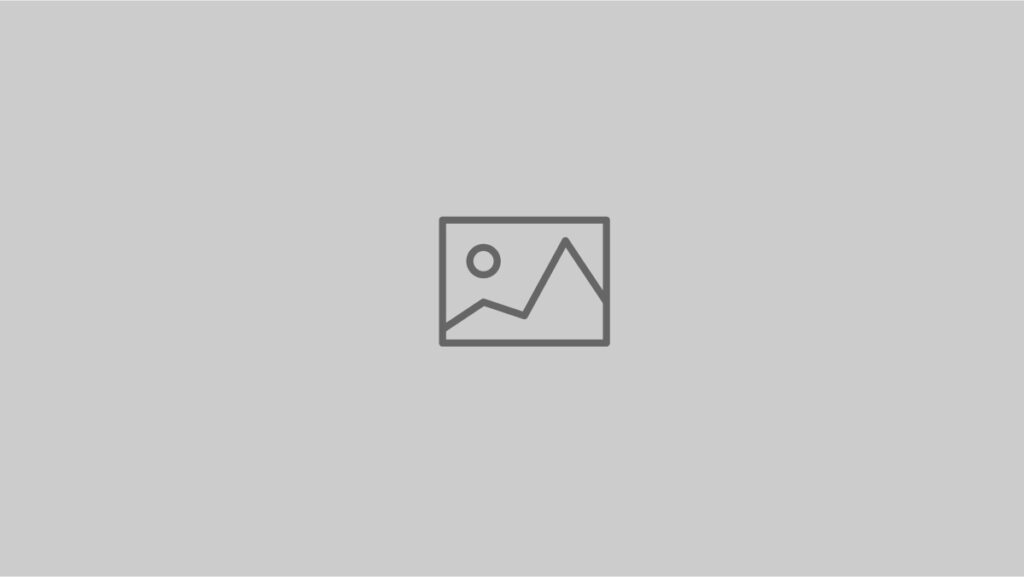
- 利用できるウィジェットの中から「カテゴリー」ウィジェットを探します。
- 「カテゴリー」ウィジェットを、表示させたいサイドバーやフッターなどのウィジェットエリアにドラッグ&ドロップします。
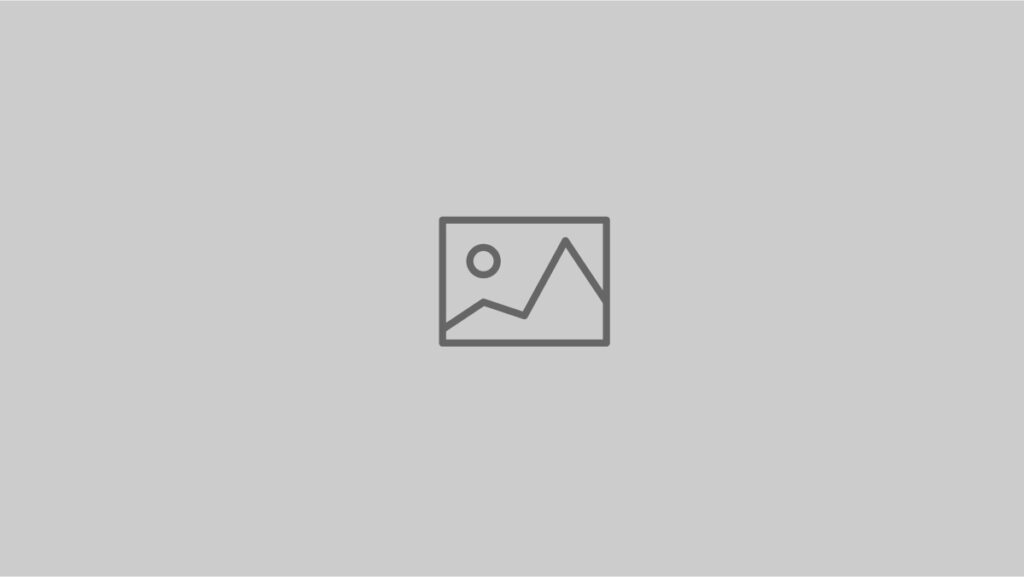
- ウィジェットのタイトル(例:「記事カテゴリー」「情報カテゴリ」など)を設定し、「投稿数を表示」や「ドロップダウンで表示」などのオプションを必要に応じて設定します。
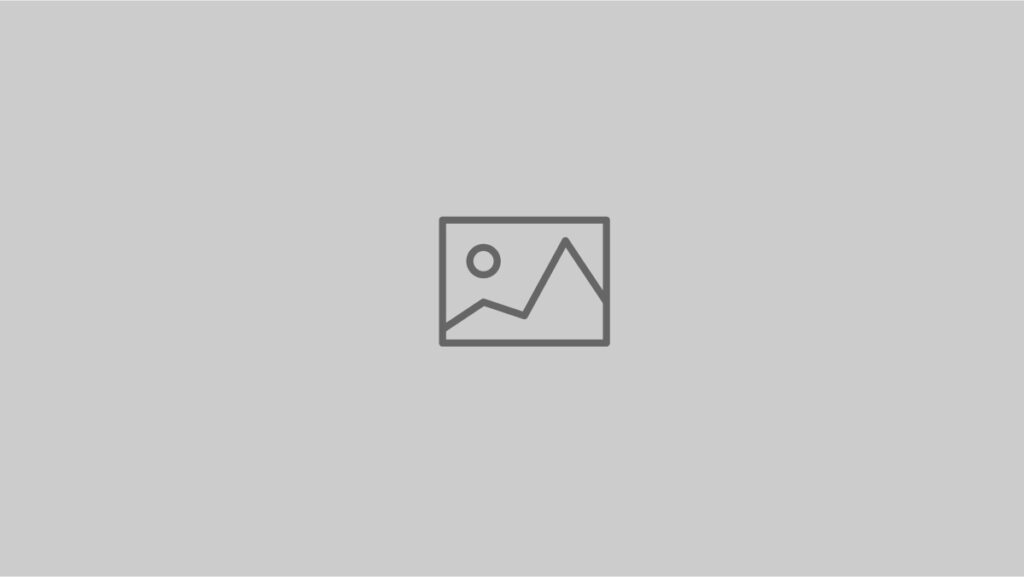
- 最後に「更新」ボタンをクリックすれば、サイドバーにカテゴリーの一覧が表示されます。
これらの方法でカテゴリーをサイトに表示させることで、訪問者は効率的に目的の情報へとアクセスできるようになります。
知っておくとさらに便利!カテゴリー活用の応用術
WordPressのカテゴリーの基本はマスターできましたか?
ここからは、さらにサイトを使いやすく、検索エンジンに強くするための応用テクニックをご紹介します。これらの知識があれば、あなたのサイトはもう一歩上のレベルに引き上がります。
カテゴリーのスラッグを理解しよう:URLを最適化するコツ
先ほどカテゴリー作成の際に少し触れた「スラッグ」は、ウェブサイトのURLの一部として使われる非常に重要な要素です。
スラッグは、カテゴリー名を表す半角英数字の文字列で、通常はカテゴリー名をローマ字や英単語にしたものを使用します。
たとえば、「施工事例」というカテゴリー名であれば、スラッグはseko-jireiやworksとするのが一般的です。このスラッグが設定されると、そのカテゴリーページのURLはhttps://あなたのサイトのURL/category/seko-jirei/のようになります。
- URLの可読性向上:日本語のカテゴリー名がそのままURLになると、ブラウザによっては
%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E4%BE%8Bのように読みにくい文字列(エンコード)になってしまいます。スラッグを英数字にすることで、見た目がスッキリし、ユーザーにとってもわかりやすいURLになります。 - SEOへの好影響:検索エンジンはURLの文字列からもそのページの内容を判断しています。内容を推測しやすいキーワードが含まれたスラッグは、検索エンジンがカテゴリーページの内容を理解するのに役立ち、間接的にSEOに良い影響を与える可能性があります。
- 共有のしやすさ:シンプルでわかりやすいURLなら、SNSでのシェアなどもしやすく、ユーザーフレンドリーです。
カテゴリーの設定時には、以下のポイントに注意して適切なスラッグを設定しましょう。
- 半角英数字とハイフンのみで作成する:スペースや日本語、特殊文字は使わず、単語の区切りはハイフン(-)でつなぎましょう。
- 内容を推測できるキーワード:一目見てカテゴリーの内容がわかるようなキーワードを含めるとよいでしょう。
- 一度決めたら安易に変更しない:公開後にスラッグを変更すると、古いURLが使えなくなり、検索エンジンからの評価がリセットされたり、訪問者がエラーページにたどり着いてしまったりする可能性があります。どうしても変更する場合は、リダイレクト設定(古いURLから新しいURLへ自動的に転送する設定)が必須になります。
親子カテゴリーで階層を作る:複雑な情報を整理するテクニック
カテゴリーは、さらに細かく情報を整理するために「親子関係」を持たせることができます。
これは、大きな分類の下に、さらに小さな分類を作るイメージです。
親カテゴリー:施工事例
┃
┗ 子カテゴリー:戸建てリフォーム
┃
┗ 子カテゴリー:マンションリノベーション
┃
┗ 子カテゴリー:店舗デザイン
親カテゴリー:メニュー
┃
┗ 子カテゴリー:ドリンク
┃
┗ 子カテゴリー:フード
┃
┗ 子カテゴリー:デザート
このように階層化することで、より多くの情報を体系的に整理し、サイト訪問者が特定の情報に深くアクセスしたい場合に迷子にならないようにできます。
特に、扱っている情報量が多いサイトや、専門性の高い情報を提供する士業のサイトなどでは有効です。
ただし、階層を深くしすぎるとかえって複雑になって逆効果の場合もあります。多くても2階層くらいを目安にするのがおすすめです。
- 情報構造の明確化:サイト全体の情報がより論理的に整理され、検索エンジンにも理解されやすくなります。
- ユーザー体験の向上:ユーザーが求めている情報へ、段階的に深く掘り下げてアクセスできるようになります。
- ナビゲーションの改善:メニューやパンくずリスト(現在位置を示すナビゲーション)で、階層構造を視覚的に表現できます。
設定方法は、カテゴリーの新規作成画面、または既存カテゴリーの編集画面で「親カテゴリー」のドロップダウンから選択するだけです。
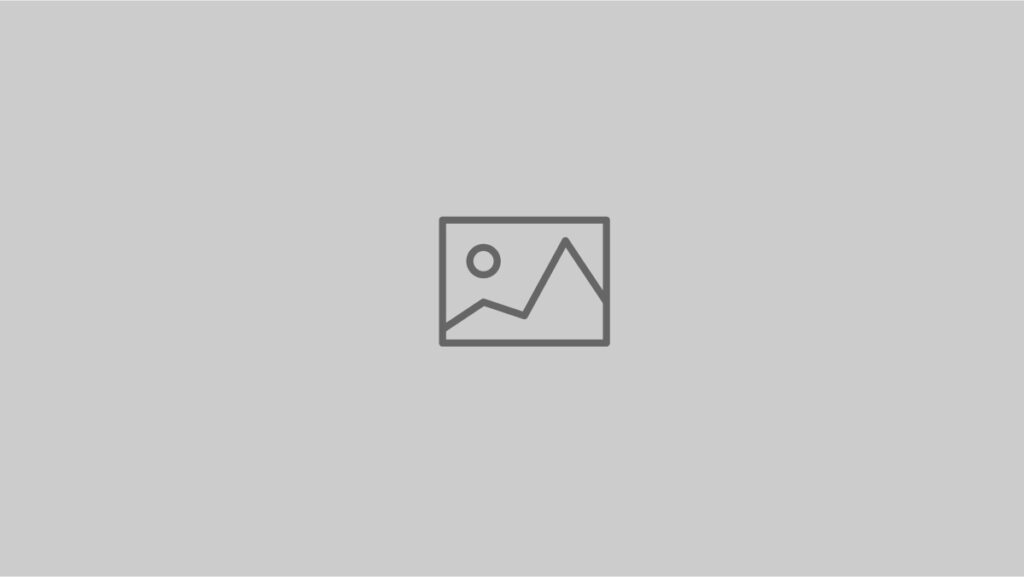
複数カテゴリー設定の注意点:ごちゃ混ぜはNG!
WordPressでは、1つの記事に対して複数のカテゴリーを割り当てることも可能ですが、基本的には、1つの記事には最も関連性の高いカテゴリーを1つだけ設定することをおすすめします。
たとえば、あるリフォームの施工事例記事が「戸建てリフォーム」と「LDK改修」のどちらにも当てはまる場合、その記事のメインテーマがどちらであるかを判断し、1つに絞りましょう。
- 重複コンテンツのリスク:複数のカテゴリーに属する記事は、それぞれのカテゴリーページで同じ内容が表示されることになります。これは検索エンジンから「重複コンテンツ」とみなされ、評価が分散したり、場合によってはペナルティを受けるリスクがあります。
- ユーザーの混乱:訪問者が特定のカテゴリーページを見たときに、関連性の薄い記事が混ざっていると、情報が整理されていないと感じ、サイトへの信頼感が損なわれる可能性があります。
- サイト構造の曖昧: 記事が複数のカテゴリーにまたがると、サイト全体の情報構造が曖昧になり、検索エンジンがサイトのテーマを正確に把握しにくくなります。
もし、複数の側面を持つ記事の場合、メインのカテゴリーを1つ選び、別途タグ機能を活用して、補足的なキーワードを付与するのがいい方法です。タグについて詳しくは以下の記事で解説しています。
あなたのサイトに合ったカテゴリー設計の考え方
ここまで、カテゴリーの重要性や設定方法、応用術について理解が深まったと思います。
ここからは、あなたのビジネスや活動内容に合わせ、どのようなカテゴリー設計をするべきか、具体的な事例サンプルで考えていきましょう。
小規模法人・個人事業主向け:まずはシンプルに!3~5個から始めよう
「PC得意だよね?」とWeb担当を任された小規模法人のスタッフの方や、リフォーム・整体など地域密着型サービスを提供されている個人事業主の方などは、まずシンプルに、核となる情報を整理することから始めるのがおすすめです。
会社概要や料金プランといった固定的な情報は「固定ページ」で作成することを念頭に置き、カテゴリーは「新着情報」や「実績」など、継続的に追加・更新していく情報の分類に使いましょう。
- お知らせ/新着情報:営業時間変更、キャンペーン、臨時休業など、タイムリーな情報を発信する
- 事例/実績:施工事例、お客様の声、導入事例など、具体的な成果や体験談を紹介する
- ブログ/コラム:サービスに関する役立つ情報、業界トレンド、日々の出来事などを記事として発信する
たとえば、リフォーム会社なら「施工事例」「お客様の声」「お知らせ」「ブログ」といった具合です。これだけでも、サイトの目的を十分に果たせるはずです。
- 最初は少なめに:まずは3〜5個程度の主要なカテゴリーに絞りましょう。情報が増えてきたら、徐々に細分化していく方が混乱を避けられます。
- 訪問者目線で考える:あなたが提供したい情報ではなく、訪問者が「何を知りたいか」を最優先に考え、それに合わせたカテゴリー名にしましょう。専門用語は避け、一般的な言葉で表現するのがおすすめです。
- メインメニューに配置:最も重要なカテゴリーは、サイトのメインメニューに配置して、いつでもアクセスできるようにしましょう。
士業・NPO向け:信頼性と分かりやすさを両立するコツ
地方で開業されている税理士や行政書士といった士業の方、あるいは小規模NPOや地域団体のボランティア運営者の方などは、Webサイトで信頼感を伝え、活動内容を明確にすることは非常に重要です。
カテゴリーは、専門的な情報や活動報告を体系的に発信するために活用しましょう。
- お知らせ/活動報告:最新のセミナー・イベント情報、法改正情報、イベントレポート、ボランティア活動の様子などを発信する
- 解決事例/実績:過去の相談事例や解決実績、具体的な活動の成果を記事として紹介する
- コラム/専門解説:専門分野に関する解説記事、税務のヒント、行政手続きのポイントなど、読者に役立つ情報を提供する
たとえば、税理士なら「解決事例」「専門コラム」「お知らせ」といった構成が考えられます。これにより、専門性と信頼性を効果的に伝えられます。
- 信頼性・フォーマルさを重視: カテゴリー名も「〜について」「〜のご案内」など、丁寧な表記を心がけましょう。
- 専門性と分かりやすさのバランス:専門的な内容でも、初心者の方が理解できるよう平易な言葉で解説するカテゴリーを用意しましょう。
- 透明性の確保:特にNPOの場合、活動報告や会計報告など、透明性を示すカテゴリーは信頼感に直結します。
店舗・スモールビジネス向け:「身近で温かみのあるブランド」を作るサイト運用方法
夫婦でカフェを経営しているなど、SNSでの発信だけでなく、見た目にもこだわりつつ簡単にサイトを作りたいスモールビジネスを営む方は、温かみのあるブランドイメージをWebサイトでも表現し、来店や問い合わせにつなげましょう。
カテゴリーは、お店の魅力や最新情報をタイムリーに伝えるために活用します。
- お知らせ/新着情報:季節限定メニューの開始、イベント情報、営業時間変更、臨時休業など、タイムリーな情報
- 日々のできごと/ブログ:店でのちょっとしたエピソード、新しい食材の紹介、スタッフの紹介など、親しみやすさを伝える内容
- ギャラリー/フォト:お店の雰囲気や商品の美しい写真をまとめて見せる。「ギャラリー」「お店の雰囲気」など
- メディア掲載/イベントレポート:雑誌やテレビでの紹介、開催したイベントの報告など
たとえば、カフェなら「新着情報」「日々のブログ」「ギャラリー」といった構成が、来店を促す上で非常に効果的です。
- ビジュアルを重視:写真が映えるカテゴリー設計を意識しましょう。「ギャラリー」など、写真メインのカテゴリーを設けるのも効果的です。
- 個性を表現:他店・競合との差別化を図るため、こだわりやコンセプトを伝えるカテゴリーを設けることが重要です。
- 最新情報の更新:季節限定メニューやイベントなど、頻繁に更新する情報をまとめるカテゴリーは訪問者のリピートに繋がります。
よくある質問:カテゴリーに関する疑問を解決!
カテゴリーとタグ、何が違うの?使い分けのポイントは?
WordPressにはカテゴリーとタグという似た機能がありますが、役割は異なります。
カテゴリーは記事を大まかに分類するための「大きな棚」のようなものです。 階層構造を持たせることができ、1つの記事には通常、最も関連性の高いカテゴリーを1つか2つ設定します。たとえば、「施工事例」や「お知らせ」などがこれにあたります。
一方、タグは記事内の細かいキーワードやトピックを関連付ける「索引」のようなものです。 階層は持たず、一つの記事に複数設定できます。たとえば、ある施工事例の記事に「LDK改修」や「水回り」といった具体的な内容を示すタグをつけるイメージです。
カテゴリーで大枠を整理し、タグで詳細なキーワードを補足すると、ユーザーはより効率的に情報を見つけられます。
カテゴリー名を後から変更しても大丈夫?
カテゴリー名自体は後から変更可能です。WordPressの管理画面から簡単に修正できます。
ただし、カテゴリー名を変更すると、そのカテゴリーページのスラッグ(URLの一部)も自動的に変わることがあります。 スラッグが変わってしまうと、以前のURLでアクセスしたユーザーはエラーページに飛んでしまい、検索エンジンの評価にも影響が出る可能性があります。
そのため、もしスラッグも変更される場合は、古いURLから新しいURLへ自動的に転送するリダイレクト設定を必ず行いましょう。Redirectionのようなプラグインが便利です。
サイト公開後は、SEOやユーザー体験への影響を考慮し、安易な変更は避けるのが賢明です。
カテゴリーが多すぎるとどうなる?最適な数の目安は?
カテゴリーが多すぎると、サイトが複雑になり、ユーザーが情報を探しにくくなります。ナビゲーションメニューなどが ごちゃごちゃしているように見え、どこをクリックすればいいか迷わせてしまうかもしれません。
また、各カテゴリーに属する記事数が少なくなり、「コンテンツが薄い」と検索エンジンに判断され、SEO上不利になる可能性もあります。
最適なカテゴリー数は、サイトの規模や扱う情報の種類によって異なりますが、一般的には5〜10個程度が望ましいとされています。 小規模なサイトであれば、まずは3〜5個程度から始め、情報量が増えたら徐々に細分化を検討するのが良いでしょう。最も重要なのは、ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるか、という視点でカテゴリーを設計することです。
まとめ|WordPressのカテゴリーを使いこなして、効果的なサイトを育てよう!
この記事では、WordPress初心者の方でも会社の紹介サイトや集客サイトを効率的に構築できるよう、カテゴリー機能の重要性から具体的な設定方法、そして活用術までを詳しく解説しました。
カテゴリーは、単なる記事の分類機能ではなく、訪問者の利便性を高め、検索エンジンからの評価を向上させるための、サイト構築における非常に強力なツールです。
- カテゴリーは記事を整理する「棚」の役割を果たします
- カテゴリー設定は訪問者の利便性を高め、SEOにも良い影響を与えます
- WordPress管理画面からカテゴリーは簡単に設定できます
- スラッグと親子カテゴリーでサイトの構造をさらに強化できます
- サイトの目的に合わせてカテゴリーを設計することが重要です
適切なカテゴリー設計は、サイトの目的達成に直結します。 低コストで、自分のペースで、そして実用的なサイトを自力で立ち上げるためには、この基本をしっかりと押さえることが成功への近道です。
WordPressのカテゴリー機能を使いこなし、あなたのウェブサイトをより分かりやすく、より魅力的な情報発信の場へと育てていきましょう。
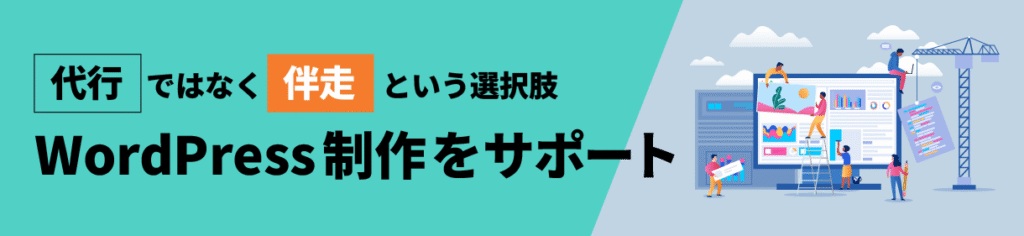
「自分でやってみたいけど、ここだけがうまくいかない…」
そんな時は、必要なところだけ頼れる「伴走型サポート」を活用してみませんか?
- サイト制作をできるだけ自力で進めたい
- 途中でつまずいた時だけ、スポットで相談したい
- 操作や設定、デザインのカスタマイズについて聞きたい